ショアジギングで青物のレンジを見極めたい

ショアジギンクでは狙う青物のレンジの認識が釣果に直結することが多いです。
浮いているのか、沈んでいるのか?
青物は海中の何処の「タナ」レンジに潜んでいるのか知りたい!知りた過ぎる。
だって、青物が居るレンジを知る音が出来れば、あの心躍るファイトの瞬間を味わえるチャンスが各段に高まるではないですか。
でも、僕たちは海に潜って見ることはてきない。
あーなんてこった・・・。
今回はショアジギンクで青物のレンゾを見極める方法を考えてみす。
基本!ショアジギングで狙う青物のレンジの一般的理解
ショアジギングで狙う青物のレンジの深さには、基本的な解釈が存在します。
表にしたので先ずはそれを理解しておきましょう。
| 状況 | レンジ | |
|---|---|---|
| 朝マヅメ 夕マヅメ | 表層〜中層 (0〜10m) | ベイトを追って浮く 表層〜中層のジグ早巻きミノーが有効。 |
| 日中 太陽が高い | 中層〜ボトム (10〜20m) | 光量が強いと沈む傾向。 スローなジグ操作が有効 |
| 潮が速い ベイトが散る | 中層中心 | ジグをレンジキープ ドリフト気味に通すと効果的 |
| ベイトが底付近 荒れた海面 | ボトム〜5m上 | 青物もボトム付近を回遊 着底から5回転以内が勝負 |
| ベイトが表層 トビウオ・カマスなど | 表層(0〜5m) | トップ系(ポッパー、ペンシル) ジグの早巻き |
ショアジギングで青物のレンジを見極める方法
朝マズメの釣果と昼過ぎの釣果違いすぎて風邪ひきそう
— ユウ (@mulch25431) January 11, 2024
あ、酒田でまだまだサゴシ釣れてます#ショアジギング #釣り #酒田 pic.twitter.com/9PLhI5grdi
青物が泳いでいるレンジ、あるいはベイトを補食しているレンジを見つけられたら釣果は確実にアップするでしょう。
基本的には
朝マズメ、夕マズメは浮きやすい
日の高い日中は沈みやすい
という原則はあります。
補食のスイッチが入った青物が浮いているから朝マズメ、夕マズメは釣り易いともいえます。
他に青物のレンジを見極める具体的な方法はあるでしょうか?
朝マズメで青物が浮いているそんな時はこのルアー
青物が浮きやすい時期に使うと釣果が出やすいのがミノー系です。
えっショアジギングってメタルジグだけじゃないの?
そんな風に驚く方もいると思いますが、ミノーやシンペンはショアジギングの奥の手の一つとして非常に有効です。
ミノーのアクションは基本的にはタダ巻きでOKです。
泳ぎが得意でアピール力が強いミノーはタダ巻きだけで十分。
小魚が逃げてる状況を意識しながらリトリーブします。
ショアジギング!海が荒れてるとベイトは沈む!?
夕方からショアジギングに行ったけど荒れてたので中止し、テトラ帯のサラシゲームをやったらクロダイが大当たり!
— fumiya (@spz238) August 17, 2019
三回ヒットしたが1匹目はタモ入れ時にバラし、2匹目はテトラにズリ上げたら落ち、3匹目でようやくキャッチ。
サイズは47cm、ヒットルアーはコルトスナイパー ロックドリフト pic.twitter.com/bKlI9Ot4bH
海面が荒れていると弱い魚は沈みがち
青物が補食するベイトの動きや、海鳥の様子からレンジを予測することご出来ます。
ベイトが浮いていれば青物も浮くし、ベイトが沈めば青物も沈むという考え方です。
比較的浅いレンジを泳ぐベイトですが、海面が荒れていると遊泳力の弱い小魚はレンジを下げる傾向にあります。
沈んだベイトを捕食する青物に効くルアー
ショアスローの良い所は魚種を選ばない「何でも釣れちゃう♪」所にも有ります。
青物はもちろんですが、ハタ系の根魚にもボトムでフラフラと誘うスロー系アクションは抜群のアピール力です。
スロー系のジグは沈みがちの青物に良く効きます。沈んでいる青物と浮いている青物を比較すれば、浮いてる方が食い気が立っている状態が多いです。
逆に言えば、沈んでいる青物ってやる気がない場合が多い…。
でも、やる気がない青物にもゆっくりフォールでネチネチ誘ってやれば、思わずパクッてくることがあるんです。
いまいち反応が薄いな…そんな日に使ってみるのもおすすめです。
鳥の動きでレンジの予測
本日のショアジギング🎣
— GEKIATSU(激アツ)🇯🇵🇦🇺 (@gekiatsufishing) January 11, 2019
遂にライザーベイトで激マサGET‼️
しかも2発‼️
でも小さいw
ライザーベイト入魂ってことで激アツベイトと名付けようw
あと小規模のナブラが発生したから、ジグで表層早まきしたらハガツオ食ってきた‼️おまけでハガツオ🐟
激アツベイト激アツ☀️w pic.twitter.com/dCCFLEwrHb
鳥の高度が低いとベイトが浮いて…る⁉
鳥がたくさん居ればベイトの濃度が高いという指標になります。
さらに海中に頻繁にダイブしていれば表層に浮いている可能性が高い。
ベイトの小魚は空に危険があることは宣告承知なはずてす。
その危険をおかしてまで浮いてくるのはエサがあるか、海中で青物に追われているからです。
鳥が盛んに海に突っ込んでいたら大チャンスです。
逆に鳥は居るけれど、空で旋回を繰り返している状況ならベイトは沈んで居るかもしれません。
鳥の高度でベイトの浮き沈みも分かる!?
特に、鳥が飛行している高度が高ければ、小魚を広い範囲で散策している…浮いている小魚を見つけられていないという状況でしょう。
逆に鳥の高度が下がってこれば、小魚の群れを見つけ的を絞り始めていると考えられます。
つまり、小魚が鳥が視認できる程度には浮いているということです。
青物が浮いているのが分かれば、ライトタックルで釣るショアジギングのホッパーゲームも超面白いです。
ホッパーで超表層を狙うから派手なバイトが直接見れちゃう♪
ショアジギングでホッパーを使うときのアクションは「連続ホッピング」です。
簡単に言えばロッドの先端をやや強めにチョンチョンとジャークさせ、ホッパーが水しぶきを上げる程度に動かすこと。
超表層だから、青物がチェイスして追いかけてくる姿も見ることができます。
ナブラがあれば大チャンス
ブリ釣り第二陣‼️
— Northern Brillin【ノーザン ブリリン】 (@NorthernBrillin) August 6, 2025
夏の戦いは続きます🐟https://t.co/19cCKBA7Dg#北海道 #北海道釣り #道南 #道南釣り #釣り #青物 #鰤 #ぶり #ブリ #ワラサ #ハマチ #イナダ #メジロ #ショアブリ #コルトスナイパーbb #ストラディックSW #ショアジギング #ショアジギ #fishing #yellowtail #ナブラ pic.twitter.com/m7PIqtPxJU
ナブラは青物浮きまくり大チャンス
ナブラが視認できれば大チャンスてす。
ベイトが顔面から飛び跳ねるようなナブラなら表層レンジ。
ベイトが視認できるだけなら中層のレンジの可能性が高いです。
カウントを取ってレンジを把握する
カウントはレンジ把握に必須の作業です。
着低から何カウントでリトリーブするのか?
あるいはボトムからどのくらい浮かせているのか?
アタリがあったら同じレンジを意識することでヒットに持ち込める可能性と再現性が高くなります。
ショアジギングではナブラに届かない!?飛距離を稼ぐ
ショアジギングでは飛距離が正義と言っても過言ではありません。
だって、ナブラが立って青物が確実にそこにいるのが分かっても、ジグが届かなかったら絶対に釣れない…。
とにかく、もっと遠くへ、飛距離を稼ぎたい。
ショアジギングで飛距離を稼ぐにはジグのバランスを意識するのも重要です。
メタルジグには前重心、中央重心、後方重心の3パターンがあります。
それぞれ、フロント、センター、リア、バランスと呼ばれます。
この中で飛距離が出るのはリアバランスです。
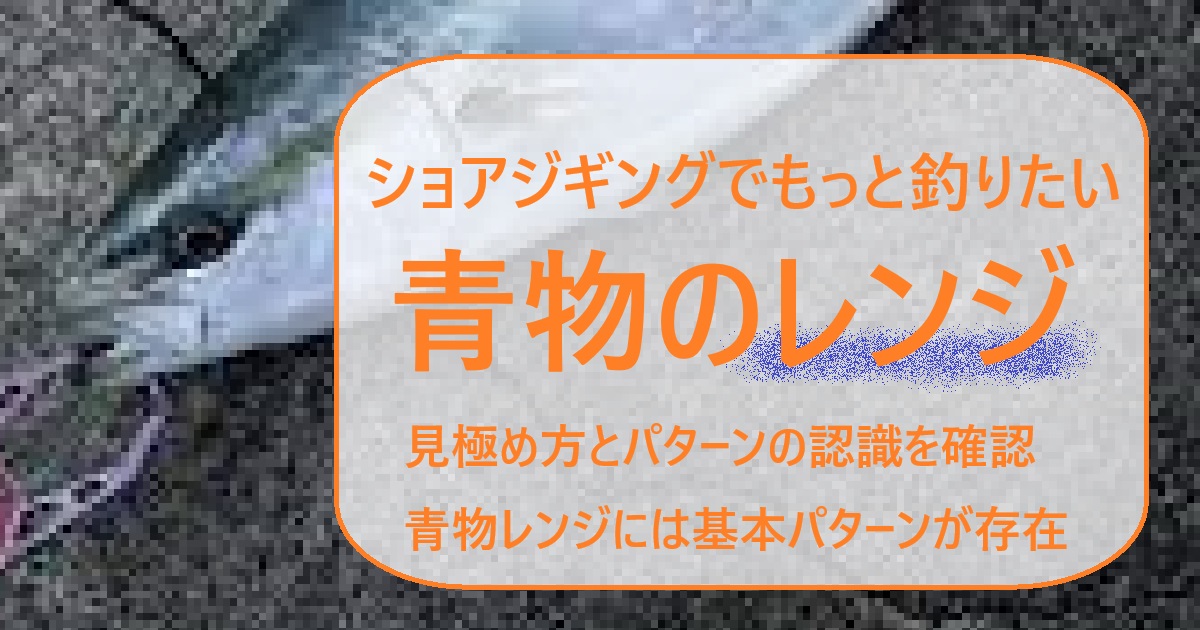




コメント